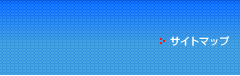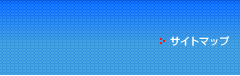���p���ɑ���זE�ڐA�ɂ���
- ���E���Ńh�i�[�p�����s�����Ă���A�זE�ڐA�Ɋ��҂��W�܂��Ă���B�|�{�p������זE�ڐA�͈ȑO���猤������Ă������A�����O�[�����˂��邾���ł͊p���̗����ɐڒ��ł��Ȃ������B
- �����搶��ROCK�j�Q�܂̊p������ւ�3�̌��ʂ����ꂽ�B
- 1.�זE�ڒ����i
- 2.�זE���B���i
- 3.�A�|�g�[�V�X�}��
- �E�T�M�ƃT���̎����ɂāAROCK�j�Q�܂p�����p������זE�����ɐ������ꂽ�B
- ���̑��ɂ��A�f�X�����ɑ��������ł���LM511����ɓK���Ă��邱�ƂȂǂ����ꂽ�B
- 2013�N�ɔ|�{�p������זE�{ROCK�j�Q�܂�O�[���ɒ�������Տ��������J�n����A11�l��10�l�Ő������A������5�N���_�ł��ǍD�Ȏ��͂��ێ��ł��Ă����B
���p������זE�����̐��i����
- ���i���ɂ͈ȉ��̂悤�Ȗ@�����֘A���Ă���B
- �Đ���Ó����S���m�ۖ@�F�Տ������A���R�f�ÂɊւ��@��
- ��Õi��Ë@�퓙�@�F�Đ���Ó����i�̐����̔��Ɋւ��@��
- ���i���̂��߂̃X�^�[�g�A�b�v�ɂ́A�������B�⎡���ȂǗl�X�Ȃ��Ƃ��K�v�ł���B
- �����搶�͍זE��ROCK�j�Q�܂����������������܂̊J���ɐ�������A���ݓ��{�����ɍזE���Y�{�݂�����A���E�e���ւ̗A�o��ڎw��������i�߂Ă�����B
��AI�ɂ���
- �]����AI�͖|��p���f����v��p���f���Ȃǃ^�X�N���Ƃɕ�����Ă������A��K�͌��ꃂ�f���͑��l�ȃ^�X�N�ɑΉ��\�ƂȂ��Ă���B
- �n��AI�ɂ���Ē�\�Z�őn��ꂽ���F�擾���ꂽ�������A��Ì����̑�K�͌��ꃂ�f���̊J�����g�s�b�N�ƂȂ��Ă���B
- �����搶��AI�Ŋp������Đ���Â̐����Ǘ����s���Ă��鑼�A�d�q�J���e�����쐬
- AI�AAI�ɂ�郊�n�r���]���A�Γ��ኳ�҂̃J���e�̓��e�𒊏o����AI�A�Γ���̎��Ö@���Ă���AI�A�������p�����̌�����\������AI�Ȃǂ̊J���ɂ��g����Ă�����B
���t�b�N�X�p������W�X�g���t�B�ɂ���
- �C�O�ł̓O�b�^�[�^�����ړI�Ŏ��͗ǍD�Ȃ�������DSAEK��DMEK���s������A���a4mm��DSO���s�����肵�Ă���B
- �t�b�N�X�̎��Âł͊p������זE�̏�Q�ƁA�זE�O�}�g���b�N�X�̒�����}����K�v�BTCF4�ɂ�����g���v���b�g���s�[�g�������̉\�������邪�ATGF4�ƃO�b�^�[�^�Ƃ̊֘A���`�q���ÂɊւ��Ă͌����i�K�B
- �t�b�N�X�̊��҂̊p������ɂ͍זE�O�}�g���b�N�X���ϐ��^���p�N�Ƃ��ċÏW���Ă���A���ꂪ�O�b�^�[�^�̌����ƂȂ��Ă���B
- mTOR�j�Q�܂̓^���p�N���̉ߏ萶����ϐ��^���p�N����}�����AmTOR�j�Q�܂̓_��ɂ��O�b�^�[�^�̐�����}���ł��邱�Ƃ����������Ŏ����ꂽ�B���ݑ�U���Տ����������{���ł���B
- ����A�t�b�N�X�̎��ÂɊւ��Č��s��DSO�ADMEK��DSAEK�ɉ����זE�����A��`�q���ÁA�_���Ȃǂ̔��W�����҂���Ă���B
�����^����
- �E�_���X�g���X�ƃt�b�N�X�p������W�X�g���t�B�̊֘A�ɂ���
- �ˊ֘A�͂���ƍl�����邪�A���i�K�ł͕������Ă��Ȃ����Ƃ������B������ɂ���a�ԉ�������������Ɨ��Ă�̂���B
- �E�זE�����͓���̐��A���p���ǂɂ����ʂ�����̂�
- �ˌ��݁A�����搶��60��̐��A���p���ǂɑ��זE���������{���Ă��邪�A1��������ċ�����Ȃ��p���������������Ă���B
- �E�p������זE�̓|���v�@�\�̑��ɁA�O�[���։��炩�̗ǂ���p�������炵�Ă���\��������̂ł͂Ȃ����B
- ��Pre peel��Non peel���r����ƁAPre peel�ł͖��炩�ɔ|�{�������������A�����������\��������B
- �E���������p������̍זE�������炳�Ȃ����@�͂���̂��H�@���ʂɒ�������Ƃ�肢���̂��H
- �ˌ��i�K�ł͍זE�������������ꍇ�͍Ē��������l�����Ă���A���₪�N�������Ƃ��Ă��X�e���C�h�_��ł̎��Â��������Ă���B���ʂɒ������Ă���p�������ނ��Ƃɉ����A���܂����I�Ȍ��ʂ͓����Ȃ��\���������B