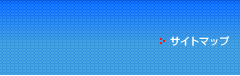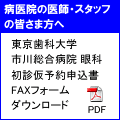![]()
結膜炎
結膜の炎症
結膜は、眼の表面で角膜以外の白目(球結膜)から連続して眼瞼の裏面(瞼結膜)まで連続して覆っている粘膜です。眼球が円滑に動かせるように結膜と眼球自体の接着は緩やかなものとなっています。ものをよく見るためには目の表面は潤っていなければなりません。結膜は涙の成分である「ムチン」という粘液を産生し、眼を乾燥から守ります。また、眼の表面は外界と直接面しているので、外からの刺激や微生物の侵入などを受けやすい部位でもあります。これらの侵入に対応できるよう結膜には免疫関連装置が備わっているので、アレルギー反応や感染などの炎症が起こりやすい場所でもあります。
結膜で起こる炎症にはいろんなものがあります。
感染性結膜炎
病原体(細菌、ウイルスなど)の感染による結膜炎
細菌性結膜炎
細菌感染により発症する結膜の炎症で、病原体の種類により症状などが異なります。黄色ブドウ球菌(staphylococcus aureus)や肺炎球菌 (streptococcus pneumoniae)の感染で発症するカタル性結膜炎は、急性に発症し、結膜充血、粘液または粘液膿性のメヤニ(眼脂)を認めます。自然治癒傾向がありますが、抗菌薬の点眼により速やかに改善します。
この他に、以前は出産時に産道感染することが多かったもので、現在は性行為時に感染することが多いものに淋菌(neisseria gonorrhoeae)やクラミジア(chlamydia trachomatis)があります。淋菌性結膜炎は膿性のメヤニが特徴で、極めて急速に進行して角膜潰瘍を起こし穿孔することもあります。クラミジア結膜炎は慢性の経過をたどり、瘢痕形成する場合があり眼球乾燥症を合併することもあります。
ウイルス感染症
- 流行性角結膜炎(epidemic keratoconjunctivitis: EKC)
- 約1週間の潜伏期の後に、眼の異物感、流涙(涙眼)、羞明(まぶしさ)や粘稠で半透明な眼脂ならびに耳前リンパ節の腫脹と圧痛を特徴とする急性結膜炎です。発症して1〜2週間目でピークとなり、その後結膜の炎症は改善してきますが、角膜に上皮障害がみられ、2〜3週間で消退します。非常に感染力が強いので、患者さんだけでなく、家族や職場の人も感染予防のために頻繁な手洗いが不可欠です。
- 咽頭結膜熱(pharyngoconjunctival fever: PCF)
- 咽頭炎、結膜炎と39〜40度の発熱を特徴とします。便中からかなり長期間にわたりウイルスが排出されるので、以前はプールで感染することが多かったために、別名プール熱ともいわれていました。約1週間程度で回復します。
- 急性出血性結膜炎(acute hemorrhagic conjunctivitis: AHC)
- 潜伏期が24時間と非常に短く、感染力も非常に強い結膜炎です。両眼の角膜上皮びらんによる異物感が強く、球結膜下の点状の出血が特徴です。1週間くらいで治癒します。
非感染性結膜炎
アレルギー性結膜炎(allergic conjunctivitis):即時型アレルギー反応で発症する結膜炎です。自覚症状として掻痒感(かゆみ)と、他覚的所見としての球結膜・瞼結膜の充血、浮腫が特徴です。抗原はハウスダスト、ダニ、 花粉、真菌、動物(イヌ、ネコ)の毛やフケなど多くのものがあります。花粉症のように毎年同じ時期に発症する季節性を示すものと、ダニ、真菌、動物のフケなどわれわれの身のまわりに存在する常在抗原により惹起される通年性のものとに大別されます。
結膜花粉症
花粉を抗原とするアレルギー性結膜炎です。アレルギー性鼻炎を併発していることが多いですが、アトピー性皮膚炎や気管支喘息などの合併率は低いようです。抗原となる花粉の種類にはスギとイネ科植物が代表的です。
春季カタル(vernal keratoconjunctivitis)
眼瞼結膜の乳頭増殖、もしくは角膜輪部の増殖性腫脹を伴うアレルギー眼疾患で、重症化した場合に角膜上皮障害を伴うことが特徴的です。男女比は3〜4:1で男性に多く、5〜7歳頃から発症して10代後半で自然治癒傾向を示します。ダニやハウスダストに対する過敏症を有していることが多いことから、アトピー性皮膚炎や気管支喘息を合併します。このような場合に自然治癒傾向を示さずに逆に重症化することもあります。