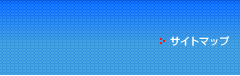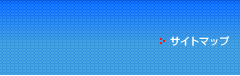���p���ڐA�̖Ɖu�}����
- ����ꂽ���ɂ̂ݓ��^�i���┽�����J��Ԃ����A�Ί�̋��┽��������������A��N�ғ��j
�V�N���X�|�����A�^�N�������X�Ȃǂ̏��ʓ��^�B�ی��K���O�B
�������t�s�S�̎���
- ���t���́A�������́A�t�ڐA
- ���t���͂�10�N�������F40�������̂܂܉��P���Ă��Ȃ�
- �t�ڐA��10�N��������98�`99%
- ���t���͂�2����1��2�`3���ԁB�������͂͊��҂���������1��4����x���������A�p���\�Ȃ̂�5�N���x
- �t�ڐA�͌��t���͂╠�����͂Ɣ�r���čP�퐫���ǂ��A�����d�����i�s���ɂ���
- ���̐t�ڐA�A���t�ڐA�Ƃ���2�N���炢�o�ƌ��t���͂��g�[�^���̈�Ô�����Ȃ�
���t�ڐA�̖Ɖu�}����
- ��ꐢ��i1960�N�j�F�A�U�`�I�v�����i�j�_�����j�Q�܁j�F�D�w�̕��ł��B��g�p�\
- ���i1980�N�j�F�V�N���X�|�����A�^�N�������X�i�J���V�j���[�����j�Q�܁j
- 2000�N�F�~�R�t�F�m�[���_���t�F�`���i�g�U�����j�Q�܁j
- 2010�N�F�G�x�������X�imTOR�j�Q�܁j
���ݐt�ڐA�Ɏg�p����Ă���Ɖu�}���ܑS�̂�90%�̓~�R�t�F�m�[���_���t�F�`���ł��邪�A���@�̓G�x�������X���ϋɓI�Ɏg���Ă���B
- �X�e���C�h�F�}�����̃p���X�Ö@�ɗp����
- �o�V���L�V�}�u�i�RCD25���m�N���[�i���R�́j�F�ڐA�̌�̕���p��}������
- ���c�L�V�}�u�i�RCD20�R�́j�AIVIG�i�O���u������ʗÖ@�j�F�RHLA�R�̂�������ɓ��^���邱�ƂŁA���}�������┽����h��
���e�X�̖Ɖu�}���܂̓���
- �Ɖu�}���܂̍�p�@��
�@T cell�F�J���V�j���[�����j�Q��
�ACTLA.4-Ig�F���{�ł͔F����Ă���Ɖu�}���܂Ȃ�
�B�j�_�����o�H�ɍ�p�F�~�R�t�F�m�[���_���t�F�`���AmTOR�j�Q��
- �V�N���X�|�����̕��p�֊�
�@�@�����N�`���A�^�N�������X�Ȃ�
- �V�N���X�|�����̕��p����
�@�@�R���B�זE�Ɖu�O���u��������
�@�@�z�X�J���l�b�g�A�A�~�m�O���R�V�h�n�R������
�@�@�o���R�}�C�V���A�K���V�N���r��
�@�@�O���[�v�t���[�c�W���[�X�i�����Z�x�㏸�������N�����j
�R�Ă��A���t�@���s�V���Ȃǁi�����Z�x�ቺ�������N�����j
�@�@�Z�C���E�I�g�M���\�E���܂ޖ�i
�@�@�X�e���C�h
ACE�j�Q�܁A�G�x�G�������X�A�~�R�t�F�m�[���_���t�F�`��
- �^�N�������X�̕��p�֊�
�@�@�����N�`���A�J���E���ێ������p��
- �^�N�������X�̕��p����
�@�@�J���V�E���h�R��A�O���[�v�t���[�c�W���[�X
�@�@�I���v���]�[���A�����\�v���W�[��
�@�@�R�Ă��A�Z�C���E�I�g�M���\�E�AST���܁A�X�e���C�h
- �Ɖu�}���܂̕���p
�@���A�a�A�������A
�@MMF�F�����i�����b�S�����t�����邱�Ƃ������j�A�n��
�@mTOR�j�Q�܁F�`���A�A�n���A�n�������x��
- ��܂��ʂɓ��^����ƕ���p�������o��̂ŁA���ܕ��p�ɂ���ƕ���p�����点��B
- ���ܕ��p�̏ꍇ��������ᇁA�����ǂ̍����ɂ͒��ӂ��K�v
������܂ł̐t�ڐA�Ɖu�}���v���g�R�[��
- �o�W���L�V�}�u�@�ڐA��2�T�ԑO���瓊�^�J�n����
- �X�e���C�h�@�ڐA����ɓ��^�J�n���A���X�ɑQ��
- MMF 1500mg�@�ڐA����ɓ��^�J�n���A
- CsA 200-300ng/mL�@�ڐA����ɓ��^�J�n���A���X�ɑQ��
- �G�x�������X 10ng/mL���瓊�^�J�n���A���X�ɑQ��
����܂ł̃v���g�R�[���ł́A�X�e���C�h�ɂ��V�K���Ǔ��A�a�A��ڍ����A������̍����ǂ�ACMV��BKV�Ȃǂ̃E�C���X�����ǂ����ƂȂ��Ă����B
�����@�ō쐬�����t�ڐA�Ɖu�}���v���g�R�[���ɂ���
- �ڐA�t�p��̌����F���������S�i�����ǁA�����V�����A�S�����A�]���Ǐ�Q�Ȃǁj���ő�
- �ĈڐA�̊����́A���{��4.6%�A�A�����J��10.6%�F���{�͍ĈڐA�̋@����Ȃ�
- �RHLA�R�̂��o���������F�����\��s�Ljȏ���A���������S�A�X�e���C�h�֘A�����ǁA�E�C���X�����ǁA�������ⓙ�����P���邱�Ƃ��d�v�@�˖Ɖu�}���܂̉��ǂƓ��Ȃɂ�錒�N�Ǘ����厖
- �G�x�������X�̗��_
�@�@CMV/BKV�Ȃǂ̃E�C���X�����ǃ��X�N�ቺ�F�E�C���X�̑��B��}����
�S���ǎ����̔��Ǘ}���F�������Ȃǂ̌��Ǔ����̑��B��}����
������ᇂ̔��Ǘ}���F������ᇂ̐V�K������Ĕ���}������
- �X�e���C�h�F��p����̋}�����̉��Ǒ�Ƃ��Ă͗L���B�܂��A���������X�e���C�h���Ƌ��┽���������Ă��܂��Ă����B���^�ʂ�������Α�����قǎ��S�����オ���Ă��܂��i���ɐS���ǃC�x���g�A�����ǂ�������j�B
- �~�R�t�F�m�[���_���t�F�`���F�J���V�j���[�����j�Q�܂݂̂Ɣ�r���Ċi�i�ɐ��������ǂ����A�����ǂ̃��X�N�������B
- ��������HLA�R�̎Y����}�����遁cAMR�ɑ��ėL��
- �J���V�j���[�����j�Q��
Acute Rejection�ɑ��ėL��
��������T cell��ˑ����̋��┽���ɑ��ėL��
�ȏ���A
�@CNI��MMF�͍ŏ��v�̂ňێ�
�A�X�e���C�h�͑����ɗ��E��ڎw��
�B�G�x�������X�͈ڐA�㑁���ɓ���
�Ńv���g�R�[����V�����쐬�����B
- �V�����v���g�R�[���F�X�e���C�h���E�����オ��A�������A�������͈ێ��ł��Ă���BCMV�̃A���`�Q�l�~�A�l���i�i�Ɍ������B�����d�����i�s�}�����Ă���B
�X�e���C�h�F�Q�����Ă����A3M�i�ڐA�t���������邱��j�Ɏ~�߂�
�G�x�������X��2w���O���炢����g�p�J�n
MMF�͓r����2000�ɑ��₵�A�܂����炷
- mTOR�j�Q�܂͌������A����A�����������̕���p������F�������ɑ��Ă͌��o�P�A���d�v�B���@�ł́A���ȉq���m�A���Ȉ�t�A�Ǘ��h�{�m�Ȃǂɂ�������Ă�����Ă���B
������
- �S���ǃC�x���g�͊�Ȃ̊��҂ł͂��܂�Ȃ����A�t�ڐA�ł͐t�@�\�����������x�[�X�Ȃ��Ƃ�����̂��A��Ȃł͓��^�ʂ����Ȃ����ߋN����Â炢�̂��H
�@�˓��^�ʂƌ��X�̑S�g��Ԃ̗����̗v�f������B
- �ڐA�㐶����3M�A1Y
�@�@1Y��������1.5M or 2M��1����x�ŊO���ʉ@�B
- �l�I�[�����͌����Z�x�̏オ������d�v�B������2���Ԃ̒l�𑪒肷��悤�ɁB
- �^�N�������X�F�Œጌ���Z�x���d�v�B3�Ő�ƖƉu�}�����ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A5�ȏゾ�Ɠ��A�a�̔��Ǘ���������B5�O��ł̈ێ���ڎw���B
- �p���ňڐA���N����Â炢�̂͑g�D������������H
�T�C�Y���֘A������Ǝv����B
�p���ڐA�ɂ��R�̗}�����B��Ă���\���͂���̂ł͂Ȃ����B���Ɋp���͌��ǂ��Ȃ��g�D�����炩�H
- �R�̂͑S�g�ŏ㏸����̂��H
�@�R�̂͏��ʂł�����̌����ƂȂ肤�邽�߁A�p�������ɏo�邱�Ƃ����邩������Ȃ��H
�@�Z���Z�v�g�͊C�O�ł͊p���ڐA�ł��g���Ă���B
- �t�ڐA�͍ĈڐA�Ȃǂ̊��Ҕw�i�͕ς��Ȃ��̂��H
�@�ˊ��Ҕw�i�̈Ⴂ�ňقȂ�v���g�R�[���͍쐬���Ă��Ȃ��B�I�[���}�C�e�B�[��ڎw�����v���g�R�[�����쐬�����B�N��⌴�����ɂ�钲���Ȃǂ͊e�X�̊��҂���ɍ��킹�Ē������Ă���iIgA�t�ǂł̓X�e���C�h���c���Ȃǁj
- �t�ڐA�̐������Ɛ������͍����Ȃ��̂��H
�@�������F��������B97�`98��
�@�������F�ڐA�����t���@�\���A���͂����Ă��Ȃ���ԁB10�N�o���Ă�95%�ȏ�B�S���I�ɂ�90%�ȏ�B
�@�@�˂ǂ�����p���ڐA���ǂ��B
�@���̐t�ڐA�̃h�i�[��70�܂ŁB���ǁA���ۉ����������Ɋւ��B
- �}�����┽���A�������┽���̈Ⴂ�́H
�@�@�ːi�s�̎��Ԃŕ����Ă���B�R�̌����Ȃǂ��Q�l�ɂ���B�ŏI�f�f�͐t�����Ŋm�F�B
�}���F�����`1�T�ԁBT cell�ɂ���Q�B
�����F3�����`6�����BB cell���Y���������ʂ̍R�̂ɂ��_���[�W���~�ρB
- �t�ڐA��̍זE�V���̃}�[�J�[�͂���̂��H
�@�V���̃}�[�J�[�͂Ȃ��B�_���[�W�Ȃǂ̃}�[�J�[�͌��A�B�i�`���A�͐t�̃_���[�W�A�����͌��a�Ĕ��j�A�h�b�v���[�G�R�[�Ō������m�F���Ă���B