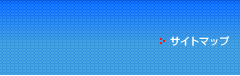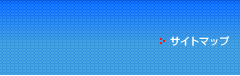混濁の範囲と程度はslitと手術室顕微鏡では見え方が異なる。
Synechia 、小瞳孔などを評価
混濁は周辺部中心
残りの角膜を通して通常通り処理できる場合も
point→CCC
混濁が中央部にかかると通常の手技では対応できない
準備
トレパンブルーを用いる
セッシのほうが針よりCCCを行いやすい
ライトガイド、シャンデリア、スリット付き顕微鏡を用いる(眼内・眼外)
混濁に隙間があるような場合はそのまま手術できることもある
ECCEはかなりみえなくてもオペは一応できることが多い
PEA
CCCが完成させられるか、中央部でUSチップが確認できるか、核分割ができるかが、溝の深さがわかるかがpoint
基本的な戦略
Syneciaはできるだけ解除
トレパンブルーを使い(後からも注入できる)CCC完成
核を4分割した後、確実に核片を処理
皮質を吸引
CCCを完成させる
トレパンブルー+眼内外照明
ヒーロンV+セッシ
高分子粘弾性物質+セッシ
前房の安定性を高めるためには
前房がいつも深々していること
核片が舞わないこと
→極小切開白内障手術が有利
前房を深く保つために
ボトルは高め(乱流を生じやすい)
吸引流量・吸引圧は落とし、チップは細く(PEA効率低下)
創口をタイトに(BSSを漏らさない)
核片を舞わせない
ボトルを下げる
吸引流量を下げる(PEA効率低下)
創口をタイトに(BSSを漏らさない)
核を離さない
白内障手術のポイント
CCCを完成させる
ライトガイドなどの照明は、奥行きがわかりにくい…D&Cよりチョップ法が
行いやすい
最後の核片の処理のとき後嚢が見難いので難しい。
皮質吸引は、取り残しに注意
|