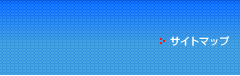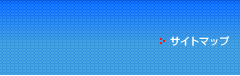小児の斜視では早期発見・治療によって正常な視力と両眼視機能を獲得することが目標である。また器質疾患や屈折異常の検出が大切である。今回は日常遭遇することの多い小児の斜視として、早期発症斜視および先天上斜筋麻痺に焦点をあてる。
小児の斜視診療のポイントは、まず小児の外観や行動をよく観察して視反応、眼位・頭位、随伴症状、全身の発達を把握し、家族から発症時期や斜視の起こり方を十分聴取することである。診察の最後には必ず散瞳して眼底検査を行い、器質疾患を否定する必要がある。特に後天斜視は注意を要し、画像診断も躊躇せず施行する。斜視の治療は、まず固視の左右差によって弱視の程度を診断し、屈折異常の完全矯正と遮閉治療(part-time occlusion)を行うことである。次に恒常性斜視には早期手術を行って両眼視機能の獲得をめざす。
早期発症斜視は難治性で正常両眼視機能の獲得は困難であるが、感受性期間内(2歳未満)の早期治療で融像や大まかな立体視が得られ、最近は1歳あるいは生後6ヵ月未満の超早期治療による立体視の獲得が試みられている。本態性乳児内斜視では生後5ヵ月〜1歳で両内直筋大量後転術(≧5.5mm) を施行した結果約40%に立体視が得られたとの報告がある。両眼視の感受性は生後3, 4ヵ月がピークで4.6歳頃まで続く。したがって早期眼位矯正と良好な眼位保持が大切であるが、生後6ヵ月未満の内斜視には自然治癒するものも含まれる。近年の調査では生後10週以降、40△以上の大角度の内斜視を繰り返し屈折値が+3.0D以下のときには自然治癒率が低い。早期発症調節性内斜視では屈折矯正を要する。早期発症外斜視は全身合併症を有することが多く注意が必要である。
先天上斜筋麻痺は小児の麻痺性斜視の中で最も頻度が高いが、実際はHelveston が分類しているように上斜筋腱の解剖学的異常に起因する疾患である。眼性斜頸の原因、DVDと共に上下斜視の原因として高頻度であり、成人になると複視の原因となる。眼性斜頸により眼位は正位に保たれることが多く、そのため視力および両眼視機能は良好なことが多い。しかしながら上斜筋腱の解剖学的異常が高度な例では両眼視機能不良例があり、外眼筋の画像検査が診断に有用である。Parks 3 段階法によって罹患筋を鑑別し、回旋偏位は眼底の回旋を参考にする。Knapp の分類と画像診断に基づいて治療方針を決定する。両眼性上斜筋麻痺の鑑別が重要であるがMasked bilateral SO palsyが約10%にみられる。上斜筋強化手術に際し医原性Brown 症候群にも注意が必要である。
|